

失業してしまった場合に頼りになるのが「雇用保険」の存在です。離職者は雇用保険を通じて失業手当を受給したり、求職活動の支援を受けたりと、再就職に向けたさまざまなサポートを享受できます。
フルタイムで働く労働者は雇用保険に加入する義務があります。ところが、時短勤務で働く派遣社員や契約社員、アルバイト、パート社員は雇用保険への加入義務がないケースがあり、企業としてはこれらの労働者の加入条件についてしっかりと理解しておかなければなりません。特に派遣社員の場合は雇用主が派遣会社となるため、自社が雇用する労働者とは取り扱いが異なります。派遣会社と連携し、派遣先企業としての義務を果たす必要があります。
この記事では派遣社員の雇用保険を取り上げ、加入するための条件や失業手当の受給手続きについてわかりやすく解説します。
目次
- 派遣社員が雇用保険に加入するための条件
- 雇用保険の概要
- 雇用保険への加入条件
- 派遣先企業と派遣元企業の義務
- 失業保険とは?
- 失業手当を受給するための条件
- 派遣社員が失業手当を受給するための手続き
- ステップ①: 離職票の交付
- ステップ②: 受給資格の決定
- ステップ③: 雇用保険受給者説明会への出席
- ステップ④: 失業認定を受ける
- ステップ⑤: 失業手当の受給開始
- 待機期間と給付制限期間とは?
- 待機期間
- 給付制限期間
- 派遣社員の自己都合退職と会社都合退職の区別
- 自己都合退職
- 会社都合退職
- まとめ
1.派遣社員が雇用保険に加入するための条件
雇用保険はすべての労働者が加入できるものではなく、加入するには一定の条件を満たす必要があります。ここでは雇用保険の概要をはじめ、派遣社員における雇用保険の加入条件のまとめ、派遣先企業・派遣元企業の双方に生じる義務について解説します。
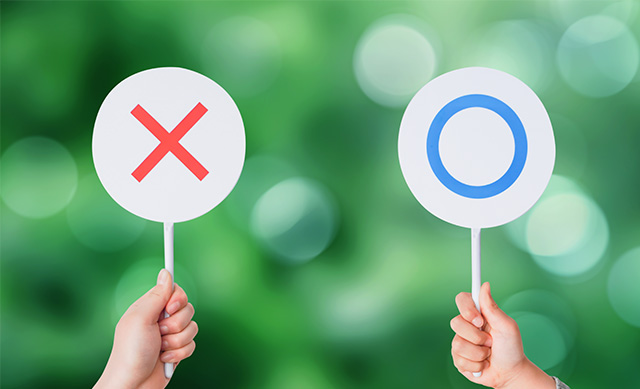
雇用保険の概要
雇用保険とは、失業手当の交付や再就職の支援など、労働者が働き続けるための総合的な支援を提供する保険制度です。失業手当は労働者が失業した場合に生活資金として給付されるもので、万一のときのセーフティネットとしての役割を果たしています。失業した労働者の生活を守り、再就職を促進するための制度といえます。
同じく労働者の生活の保障を目的とした制度に「傷病手当金」もあります。これは業務外の病気やけがの療養によって仕事に就けないときに受け取れる手当金で、健康保険から支給されます。以下の記事で詳しく解説していますので、本記事とあわせて参考になさってください。
関連記事:もしものときの傷病手当金!派遣社員の受給条件や契約終了後の適用は?
雇用保険への加入条件
雇用形態にかかわらず、次の条件を満たす労働者は雇用保険に加入できます。
- 条件①:31日以上の雇用継続見込みがあること
- 条件②:1週間の所定労働時間が20時間以上であること
上記の条件に該当していれば、派遣社員や契約社員、アルバイト、パートなども雇用保険に加入することが可能です。一部の事業を除き、条件に該当する労働者を一人でも雇っているなら、その事業主は労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きをおこなう義務があります。
条件①:31日以上の雇用継続見込み
派遣社員の場合、雇用主である派遣元企業の雇用保険に加入します。実際の就労場所である派遣先企業が変更しても、同一の派遣元企業から31日以上雇用が継続される見込みがあれば条件を充足します。
条件②:1週間の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載される従業員の労働時間(始業時刻から終業時刻までの時間から休憩を差し引いた時間)のことです。具体的には、1日4時間かつ週5日の勤務であれば条件を充足します。
なお、雇用保険料は2022年に段階的に引き上げられており、今後も動向を注視する必要があります。法改正における雇用保険料の引き上げについては以下の記事をご参照ください。
関連記事:雇用保険料率の引き上げ!2022年法改正における変更点を解説
派遣先企業と派遣元企業の義務
派遣元企業は、社会保険の資格取得に関する事実を、派遣先企業に通知しなければなりません。そして、派遣先企業は派遣元企業から通知を受けたとき、対象者の保険加入を証明する書類を確認するとともに、万一未加入であった場合には派遣元企業に加入を求める義務があります。
社会保険は現在、適用範囲が拡大されています。雇用保険以外でも労働者の加入義務について、法改正に則って判断しなければなりません。以下の記事では派遣社員をはじめとした非正規社員における社会保険の適用拡大を取り上げ、企業と個人の双方にどのような影響が及ぶのか詳しく解説しています。

