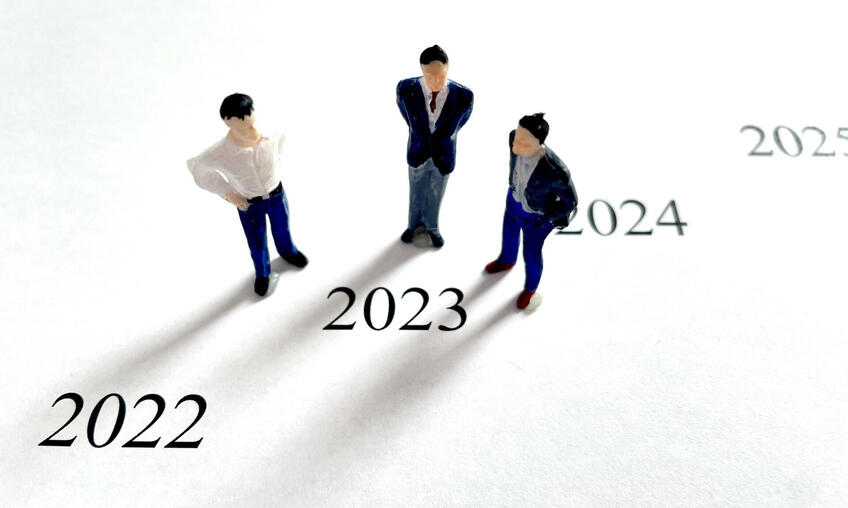

1986年の施行から2023年現在までに何度も改正されている「労働者派遣法」。適切な労働者派遣事業により派遣労働者の安全な労働環境を維持するための法律であり、派遣会社はもちろん派遣先企業や派遣労働者本人も、その内容を正しく理解しておく必要があります。
この記事では、労働者派遣法改正の歴史とともに、近年の改正ポイントから見る派遣事業の最新情報についてわかりやすく解説します。
目次
- 労働者派遣法とは?
- 労働者派遣法改正の歴史
- 近年の労働者派遣法改正のポイント
- 2020年改正のポイント:同一労働同一賃金の導入
- 2021年改正のポイント:義務の強化により労働者保護をさらに推進
- まとめ
1.労働者派遣法とは?
現在の労働者派遣法は、正式名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
1986年に労働者派遣法が施行される前は「職業安定法」のもとで労働者供給事業が禁止されていたものの、1970年代から労働者派遣のニーズが高まり市場が拡大しているという矛盾した状況にありました。
こうした状況下において、労働者保護の観点で抱えていたさまざまな問題を是正し、労働者派遣の需要に応えるために、労働者派遣事業の正しい運営を目的とした労働者派遣法が定められたのです。
その後も労働者派遣の実情や社会の状況にあわせ、法改正を繰り返しながら現在の内容に至っています。


