

現在は働き方が多様化しており、個人の事情に合わせてさまざまな雇用形態で働くことができます。しかし、派遣社員においては「担当業務の幅を広げたい」「より安定して働きたい」などの理由により、直接雇用への切り替えを希望するケースも少なくありません。
派遣から直接雇用に切り替えることは企業にとってメリットがある反面、法律上の義務も担うことになります。このため、実際に適用する場合は法律に則り、慎重に検討・対応する必要があります。
この記事では、派遣から直接雇用への切り替えについて、企業側のメリットや求められる義務をわかりやすく解説します。
目次
- 派遣社員と直接雇用、各々の特徴とは?
- 派遣社員の特徴
- 直接雇用の特徴
- 企業が派遣社員から直接雇用に切り替えるメリット
- メリット①:採用コストの抑制
- メリット②:スキル向上に伴う対応業務の拡大
- メリット③:3年以上の長期的な勤務が可能
- 企業が派遣社員から直接雇用に切り替えるデメリット
- デメリット①:労務管理コストの増大
- デメリット②:働き方の柔軟性の消失
- 派遣社員の直接雇用に関連する企業の義務
- 雇入れ努力義務
- 募集情報の提供義務
- 雇用安定措置
- 派遣社員を直接雇用する場合の手数料について
- 派遣社員を直接雇用した場合に活用できる助成金
- まとめ
1.派遣社員と直接雇用、各々の特徴とは?
派遣社員と直接雇用にはそれぞれ以下のような特徴があります。
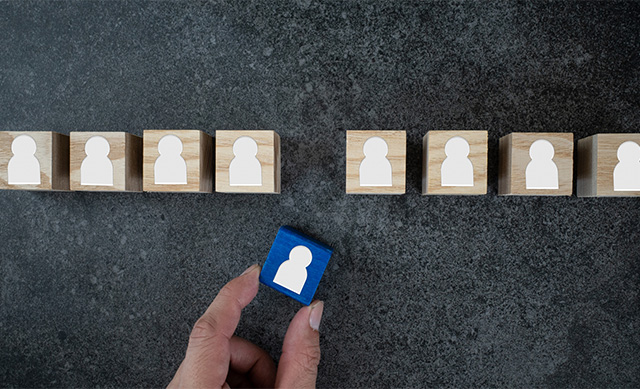
派遣社員の特徴
派遣とは、派遣元企業から派遣先企業に派遣されて働く就労形態のことです。派遣社員と雇用契約を結ぶのは派遣元企業であり、派遣社員に対する給与支給や福利厚生の用意などは派遣元企業がおこないます。
派遣は以下の3つの類型に分類されます。
- 一般派遣
一般派遣とは、仕事を求める人が人材派遣会社に登録し、希望条件に合った派遣先企業の紹介を受けて就業する働き方です。実際の就業場所となる派遣先企業が決まった後に、人材派遣会社と雇用契約を締結し、契約期間中は派遣先企業で働きます。登録型派遣ともいわれ、登録している人材派遣会社が雇用主となります。
- 紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、一定期間(最大6か月)派遣社員として就労した後、派遣先企業の直接雇用に切り替えることを前提とした働き方です。ただし、紹介予定派遣として派遣されたとしても、必ずしも派遣先企業と雇用契約を結べるとは限りません。派遣期間が終了した後の直接雇用への切り替えは、派遣社員と派遣先企業それぞれの合意のもとで決定されるからです。双方の合意があって派遣先企業の直接雇用となる場合、雇用契約は派遣先企業と締結することになります。
- 常用型派遣
常用型派遣(無期雇用派遣)とは、人材派遣会社と派遣社員が常時雇用契約を結び、派遣会社の社員として派遣先企業に就業する働き方です。派遣されている期間のみ人材派遣会社から給与の支払いを受ける一般派遣に対し、常用型派遣は派遣されていない期間中も給与が発生します。つまり、派遣先Aの派遣期間が終了し、次の派遣先Bが見つかるまでに働いていない期間ができたとしても、常用型派遣であればその期間中も派遣会社から給与が支払われることになります。給与面で安定した雇用形態といえるでしょう。
関連記事:無期雇用派遣と有期雇用派遣の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを紹介
直接雇用の特徴
派遣元企業と雇用契約を結ぶ派遣に対し、就労先の企業と雇用契約を結ぶのが直接雇用です。就労先の企業が雇用主となり、従業員の給与や福利厚生を負担します。直接雇用の契約類型として、正社員や契約社員、アルバイト、パートなどがあります。
派遣社員には同じ事業所・同じ部署で就業できる期間を最大3年とする、いわゆる「3年ルール」があります。これにより、派遣社員と派遣先企業の双方が3年を超える長期契約を希望するケースにおいて、派遣社員の就業形態を派遣から直接雇用へ切り替えることができます。この場合、派遣先企業の直接雇用となるため、雇用主も派遣元企業から派遣先企業へ変わることになります。

