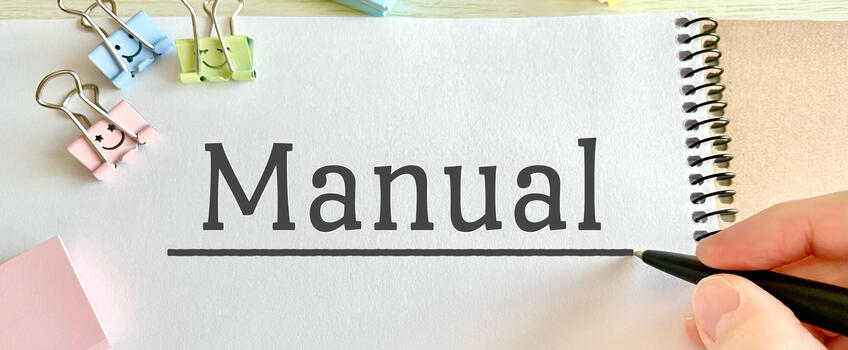
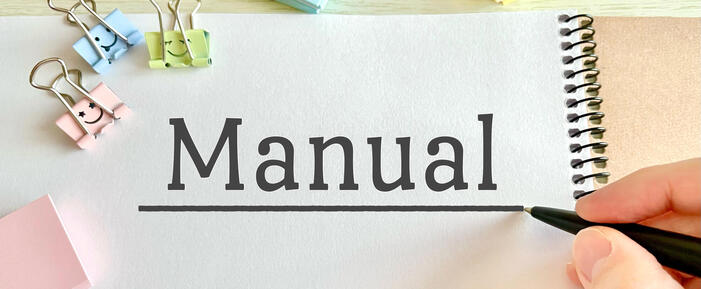
業務の目的や手順をまとめた業務マニュアルは、新しく業務を習得するうえでなくてはならないものです。マニュアルに沿って作業を進めると、業務の流れや判断に迷うことなく、誰もが一定以上の品質を担保できます。派遣社員を受け入れる際にも、マニュアルがあれば業務指導がスムーズに進むため、教える側の社員の負担が軽減されます。
この記事では、業務マニュアルの作り方やコツについてわかりやすく解説します。
目次
- 業務マニュアルとは
- 手順書との違い
- 業務マニュアルを作成する目的
- 業務の標準化
- 業務の効率化
- 顧客満足度の向上
- 教育の負担軽減
- 業務マニュアルに記載する内容
- 業務マニュアルの作り方
- 1.スケジュールを立てる
- 2.マニュアル化する業務内容を整理する
- 3.フォーマットと構成を決める
- 4.構成に沿って落とし込む
- 5.マニュアルを運用し効果を検証する
- 業務マニュアル作成のコツ
- 5W1Hを意識する
- 読み手の目線に立つ
- レイアウトを工夫する
- ミスしやすいポイントを記載する
- ITツールを活用する
- 派遣社員の受け入れに必要な準備
- まとめ
1.業務マニュアルとは
業務マニュアルとは、業務の標準的な手順を示したガイドラインのことです。その業務を遂行するうえで必要な情報が網羅的に記載されており、マニュアルに沿って作業を進めることができれば一定以上の品質を保つことができます。
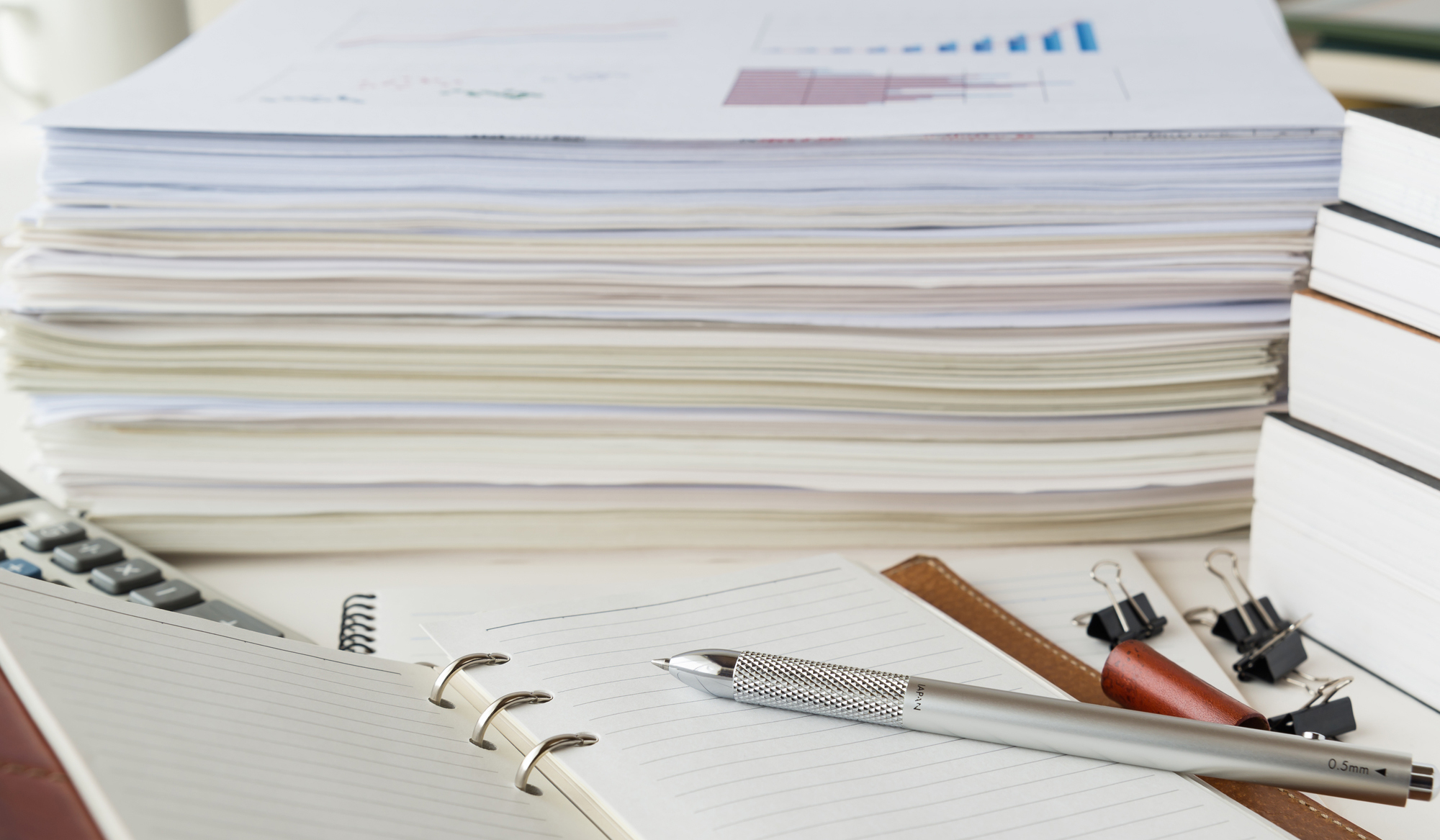
手順書との違い
業務マニュアルと類似するものに「手順書」があります。 手順書とは、一つの作業の手順について細かく記した書類のことです。一方、マニュアルは業務全体の概要や流れ、規則などを網羅的にまとめたもので、その業務に取り組むうえでのガイドラインとなります。イメージとしては、業務マニュアルから一つの作業を抜き出し、その作業の手順を詳しく説明するものが「手順書」といえます。

