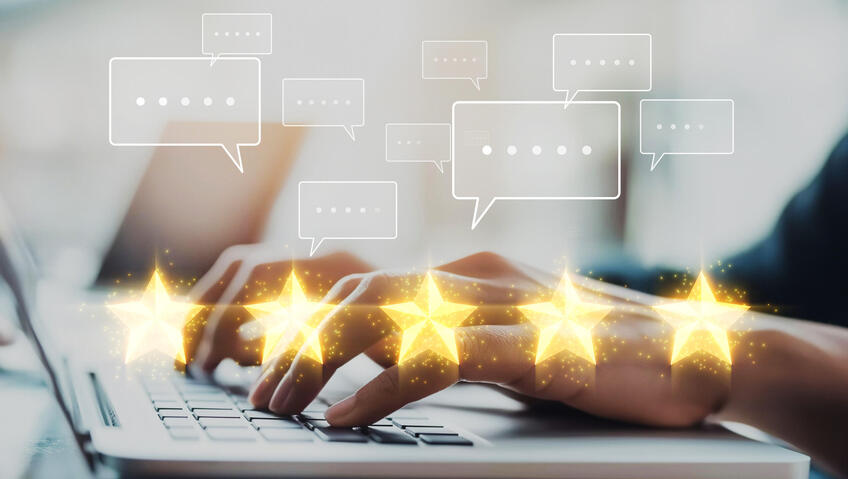

派遣社員を受け入れている企業では、派遣会社から派遣社員の評価を求められることがあります。しかし、「なぜ評価が必要なのか」「どのように評価すればよいのか」と疑問に思う派遣先担当者の方も少なくありません。派遣社員の評価は、2020年の労働者派遣法改正で規定された配慮義務と深く関係しています。そのため、派遣先企業の担当者は、評価の必要性や方法を正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、派遣社員の評価について、派遣先企業が押さえるべきポイントや配慮義務を中心に解説します。
この記事でわかること
- 労働者派遣法改正により新設された、人事評価に関する配慮義務の内容と法的位置づけ
- 派遣先均等・均衡方式と労使協定方式に基づく、派遣社員の評価方法と必要な情報提供
- 公正な評価を行うための実務上の留意点と、モチベーション向上や生産性改善につながる効果
目次
- 派遣社員の評価とは
- 派遣社員の評価が必要な理由
- 労働者派遣法の配慮義務に基づくもの
- 義務や努力義務との違い
- 派遣社員の評価方法
- 派遣先均等・均衡方式
- 労使協定方式
- 派遣社員を評価する際に押さえておくべきポイント
- 派遣会社とのすり合わせを済ませておく
- 業務内容と成果に基づいて評価する
- 評価結果を派遣料金に反映させる
- 派遣社員を適切に評価するメリット
- 派遣社員のモチベーション向上
- 生産性の向上
- 優秀な人材が集まりやすい
- 派遣社員の評価でトラブル防止のために注意すべき点
- まとめ
1.派遣社員の評価とは
派遣社員の評価とは、派遣社員の職務内容や職務遂行スキル、勤務態度、成果などを客観的に判断する取り組みを指します。
通常の職場では、同じ企業に所属する上司が部下の人事評価を行います。しかし、派遣社員の場合、派遣会社が日常の勤務状況を把握することはできません。そのため、派遣社員の業務を日頃から見ている派遣先企業に対して、評価の実施が求められます。
派遣会社は、派遣先から得られた評価を、賃金の見直しや処遇改善を行う際の判断材料として活用しています。


