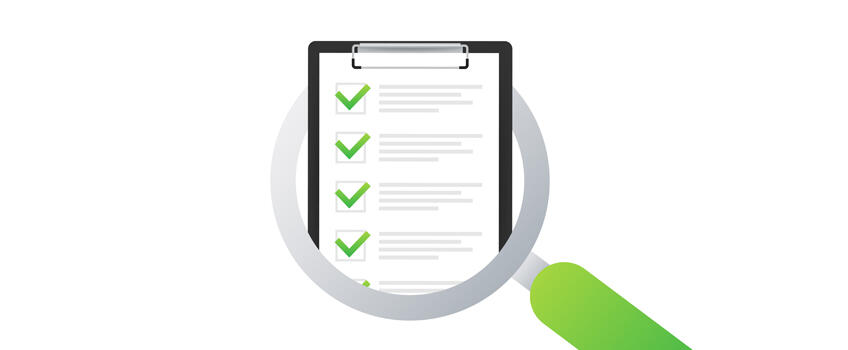
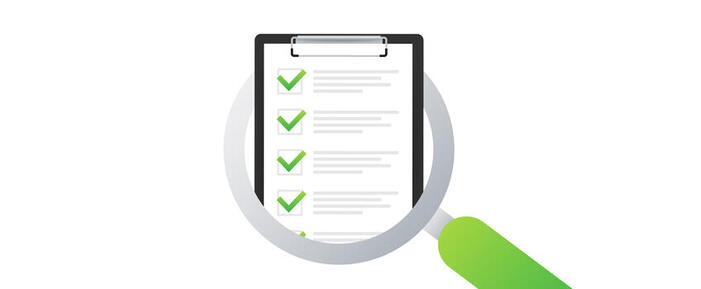
産休・育休取得者の仕事を派遣社員が代行する「産休代替」。企業にとってメリットの大きい勤務形態ですが、受け入れの際にはさまざまな準備が必要となり、通常の派遣とは異なる点についても把握しておくことが求められます。
この記事では「産休代替(産休代替派遣)」を取り上げ、一般の派遣との違いや企業が活用するメリット、受け入れに伴う注意点について詳しく解説します。
目次
- 産休代替(産休代替派遣)とは
- 産休代替で働く期間
- 産休代替の業務内容
- 産休代替と一般の派遣の違い
- 派遣期間の制限
- 担当する業務の範囲
- 企業が求めるスキルレベル
- 産休代替派遣を活用するメリット
- 必要な期間のみ人員を確保できる
- 周囲の負担軽減につながる
- 助成金の支給対象となる
- 産休代替派遣を利用するときの注意点
- 業務の引き継ぎ期間を設ける
- 引き継ぐ業務を契約書に記載する
- 3年ルールの適用対象外となる
- 派遣期間が変更する可能性を伝える
- 産休代替のよくある質問
- 契約期間の延長を断られてしまった場合、どうしたらよい?
- 社員が育休を繰り上げするため、派遣社員には別の業務をお願いできる?
- 育休終了のタイミングで社員が退職した場合、継続して働いてもらうことはできる?
- まとめ
1.産休代替(産休代替派遣)とは
産休代替(産休代替派遣)とは、産休・育休を取得する社員の代替要員として、その社員が担当していた仕事を派遣社員が請け負う勤務形態のことです。仕事と育児の両立を後押しするために、各企業において産休・育休制度を充実させる動きもあり、派遣社員による産休代替のニーズが高まっています。

産休代替で働く期間
派遣社員が産休代替で働く期間は、派遣先企業の社員が取得する「産休(産前産後休業)」と「育休(育児休業)」の期間です。基本的には引き継ぐ対象者の産休・育休期間のみ対応することになります。
労働者が取得可能な産休・育休期間は以下のように決められています。
- 産前休業の日数:出産予定日を含む6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)
- 産後休業の日数:出産の翌日から8週間以内
- 育児休業の日数:子どもが満1歳になるまで
このうち産後休業は強制的な休業となりますが、労働者が早期復帰を望む場合には医師が認める業務に限り産後6週間から復帰することができます。
また、育休の日数は原則として「満1歳になるまで」であるものの、1歳の時点で特別な事情(保育所に入所できないなど)がある労働者に関しては、最長2歳まで育休期間を延長することができます。これにより産休代替の期間はひとまず子どもが満1歳になるまで、事情によって育休期間が延長する場合には派遣期間も延びる可能性があります。
産休代替の業務内容
産休代替の場合、基本的には産休・育休を取得する社員が担当していた業務を引き継ぐことになります。産休・育休に入る社員の代替要員であるため、該当社員の業務内容を同等のレベルでこなせるスキルが必要です。また、産休代替においては一人で派遣されるケースが多く、職場に派遣社員が一人だけということもあるため、派遣先の社員と円滑なコミュニケーションがとれることも求められます。

