
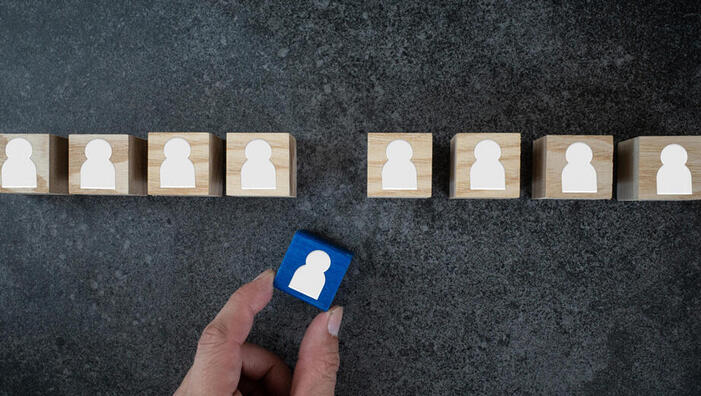
円滑な企業経営や経営活動において、特に重視すべき課題となっているのが「人手不足」です。
企業活動に必要不可欠である労働力が不足してしまうと、さまざまな悪影響やリスクをもたらします。こうした悪影響やリスクを回避するために、企業は効果的かつ早期の具体的な解決策が必要です。
この記事では、社会全体で深刻な問題となっている人手不足の原因やリスク、そして、その解決策としてピンポイントで人材派遣を活用する方法を詳しく解説していきます。
目次
- 人手不足の原因と背景
- 生産年齢人口の減少
- 人材流出
- 構造的失業
- 人手不足による企業への影響とリスク
- 既存社員の負荷増
- 労働環境の悪化
- 事業規模の縮小
- 人手不足を解消する方法は?
- 人材派遣を活用するポイント
- まとめ
1.人手不足の原因と背景
現在、多くの企業が「人手不足」に悩まされています。「採用活動を積極的におこなっているが、いい人材と巡り合えない」「候補者が集まらない」など企業を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、限られた人材を競合他社と取り合っている状況になっています。
加速している人手不足の原因や背景には、「生産年齢人口の減少」「人材流出」「構造的失業」の3つの要因が存在します。ここでは、3つの要因について解説していきます。

生産年齢人口の減少
日本の人口は2008年の約1億2,800万人をピークに減少に転じており、2060年には約8,700万人となり、同年の生産年齢人口は約4,400万人まで減少すると推計されています。
今後も人口減少は続いていくと予想されており、慢性的な人手不足のため、企業は人材獲得競争に勝ち抜いていかなければならない状況が続くでしょう。
人材流出
現在の仕事内容や待遇、環境や人間関係、社風の不一致など、あらゆるネガティブな要素を理由とした退職も人手不足の原因の一つとなっています。
近年、働き方改革によって働き方が多様化したことや、終身雇用制度の維持が見直されている日本において、社員が自身の待遇向上や働きがいを求めて、他社へと転職してしまうことは十分考えられます。
そのため、社員を定着させるための対策を講じなければ、人手不足の原因となってしまうことが予測されます。
構造的失業
構造的失業とは、企業が求める人材と求職者の持つ特性が異なるがゆえに生じる失業のことです。求職者の学歴や年齢、性別やスキル、勤務地などの労働条件が企業側の希望とマッチしないため、働く機会を得ることができない状況が発生しています。
特に、地方の求職者は大都市と比較すると求人数が少なく、希望する職種に採用枠がないことが多い傾向にあります。こうした状況から、働く意思があったとしても仕事がないという構造的な問題が、実質的な人手不足につながっているともいえます。

